ごあいさつ
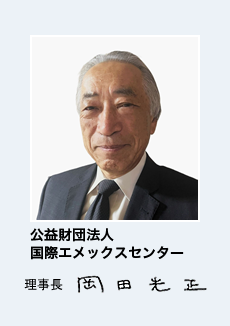
閉鎖性海域は外海だけではなく沿岸域の人間活動等を通じて陸域の影響も受けている海域、いわば陸と海とが交わる海域です。その代表ともいえる瀬戸内海は、かつて「瀕死の海」と呼ばれる状況にまで水質悪化が進んだため、総量削減を含む様々な排水規制が行われてきました。瀬戸内海のみならず、同様な問題に直面している世界の閉鎖性海域の環境の保全・創造を目的として国際エメックスセンターが設立された1994年はこのような時期にあたります。
以降、排水規制等によって瀬戸内海の水質は改善されてきましたが、近年は漁獲量の減少やノリの色落ちのように生物生産性は低迷し、水質保全だけではかつての豊かな瀬戸内海が再生されないと考えられるようになりました。このため、2015年の瀬戸内海環境保全特別措置法改正では、「生物の多様性及び生産性が確保されていること等、その有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とする」ことが盛り込まれるとともに、2021年改正では特定の海域において栄養塩類を適切に増加させることを可能にする特例も新設されました。
一方、2023年には「生物多様性国家戦略2023‐2030」が定められ、陸と海の30%以上を健全な生態系として保全する目標(30by30)が掲げられ、持続可能な産業活動が生物多様性の保全に貢献している海域を「保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域(OECM)」として認定することになりました。
このように、閉鎖性海域の環境保全は、当センター創立時のような一方的な負荷量削減から、生物多様性の確保のために負荷量管理、さらには沿岸域生態系の生物多様性の保全へと変化してきました。近年のエメックス会議等で注目されている統合的沿岸管理や里海の創生はまさにこのような変化に対応しているものです。
当センターとしてこれをさらに推進するには、行政、研究者、事業者、市民等の各主体間の有機的ネットワークを構築し、国際的かつ学術的な交流を推進することがこれまで以上に求められております。皆様の御協⼒と御⽀援、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2024年1月


