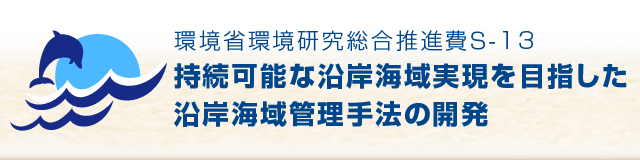2016年7月6日
平成28年度公開シンポジウムの概要
- 日時
- 平成28年5月9日(月)10:00~16:00
- 場所
- 富山県民会館
概要

平成28年度公開シンポジウムは、富山県民会館(富山市)で開催され、関係する研究者や行政関係者等が参加した。
発表では、環境省環境研究総合推進費S-13プロジェクト「持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸海域管理手法の開発」に係る研究成果についてプロジェクトメンバーから報告があり、今後の研究の方向性等について意見交換が行われた。
主催
環境省環境研究総合推進費S-13プロジェクト
(公財)環日本海環境協力センター、(公財)国際エメックスセンター
発表
1 S-13プロジェクトについて
((公財)国際エメックスセンター 柳 哲雄 氏)
S-13プロジェクトとして、環境研究総合推進費による「持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸海域管理手法の開発」が2014年にスタートし、現在3年目である。このプロジェクトは5つのテーマで構成されており、3つの自然科学分野の研究を人文・社会科学と統合数値モデルとでまとめて総括し、施策を提案する。目標は「里海」と呼ぶ「きれいで豊かで賑わいのある持続可能な沿岸海域」を実現し、その成果を世界発信することである。「領域融合」により自然科学と人文・社会科学の観点からどういう要素が管理に必要かを統合数値モデルにより「里海の定量化」することを目指したい。
対象とする3つの海域のうち、「三陸」の志津川湾では養殖のあり方を検討して「志津川湾の統合モデル」を作成し、「瀬戸内海」については「1950年の状況と2050年の瀬戸内海統合モデル」を作る。また、「日本海」については対馬暖流の状態をきちんと再現し、富山湾や若狭湾について今後どのようにすべきかを検討する。ここで、「統合」とは、陸域の影響、外洋の影響、大気の影響を社会科学の成果と「統合」しようとするものである。
研究の当初には「きれいで豊か、というのは両立しないのではないか。」ということがよく言われたが、適度な透明度と栄養塩の時に植物プランクトンが最も多く基礎生産量が最も大きくなるという「極値」があると考えられる。「豊かな海」のためには転送効率の高い海が必要である。「持続可能性」のためは「里海」の状態が望ましいと考えられ、定量化のために生態系サービスの価値のストックを計算する。一般的には、透明度・DO・TP・TNなどを海の環境指標としているが、これらは直接コントロールできないため、影響を与える要素をどのようにすればよいかをモニターしながら「統合モデル」で評価し、PDCAにより順応的管理を行うことを提案したい。これを世界に発信し世界の沿岸海域を「きれいで豊かな沿岸海域」にしていきたい。
2 閉鎖海域・瀬戸内海における栄養塩濃度管理法の開発
(広島大学 西嶋 渉)
我々は瀬戸内海をフィールドに研究をしている。瀬戸内海では1970年代は赤潮が年間300件程度発生していたが1990年ごろからは100件程度で推移している。環境基準達成率は80%程度になって以降は減少気味で推移している。
有機汚濁の改善がみられないのは内部生産が原因であり、このため栄養塩の規制が始まった。しかし、漁獲量は1980年をピークに減少しており、健全な物質循環と高い生物生産性という視点での沿岸域管理が大きなテーマになっている。
そこで、我々は光環境の問題とプランクトン食性魚について研究を行っている。クロロフィルaが0の時の透明度を「地域固有透明度」として瀬戸内海の分布を明らかにしたところ、沿岸は低い値になった。植物プランクトンが増殖しやすいところは沿岸域に限られ、赤潮発生の分布と一致した。広島湾において沿岸域と沖合の転送効率を比較したところ、沿岸域では1次生産は大きいが2次生産は小さいため転送効率は小さく、沖合では理想的な生産速度となり高い転送効率となった。
瀬戸内海の漁獲量はほぼ半減しているが、大阪湾を除く1次生産速度は16%の減少となっており、1次生産の減少が漁獲量の減少になっているとは言いにくい。イカナゴは砂地を好むものであるが、砂採取を早期に規制した兵庫県以外での漁獲量の減少が大きい。イカナゴは移動範囲が狭く、移動先に砂地がないと生育できないと考えられる。
現在、赤潮は100件程度発生しているが、発生地域は植物プランクトンが発生しやすいところに限定されてきており、生物生産性を維持するためには陸域からの栄養塩負荷削減で対応することは適切ではない。漁獲量の減少は1次生産の減少によるものとは考えにくく、イカナゴのようなプランクトン食性魚の減少について検討が必要である。
3 開放性内湾が連なる三陸沿岸海域における沿岸環境管理法の開発
(東京大学 小松 輝久)
三陸沿岸はリアス式海岸が連続し、湾口での水深が深く比較的海水交換が良い、海藻群落や岩礁藻場があるという共通性がある。この研究では、里海による生産力と生物多様性の向上のため、総括班の行う生態系モデルを使い、「きれいで豊かで賑わいのある沿岸域の創出」を行うと同時に社会的側面からも実現を模索する。
志津川湾は集水域が閉じており湾口が広いという一般的な三陸の内湾の典型となっている。陸域を含む人間が集うという内湾環境を把握し、「きれいで豊かで賑わいのある沿岸域」を創出しようとしている。
南三陸町ではフォーラムを開催し「自然と共生するまちづくり、なりわいと賑わいのまちづくり」を目指している。このためには、リモートセンシングは強力なツールとなり藻場回復過程の監視を行い、このデータを可視化し対策を立てるのに役立てようとしている。また、養殖いかだの配置を可視化して把握することができる。震災後カキ筏が大きく減少したためカキの成長が良くなっており高付加価値化へシフトしている。カキ筏やわかめ養殖筏の配置が栄養塩循環やカキの身入りにも関係することになる。
「森は海の恋人」仮説の検証を行うため栄養塩循環の全体解明を行っており湾内のマスバランスが明らかになった。カキの液体排泄量を調べた結果、栄養塩プールの7%という結果になった。鉄濃度は湾奥部は多いが、湾口部は鉄による増殖制限が起こる可能性があることが分かった。また、流出特性からは植林は針葉樹よりも広葉樹のほうが良いことが分かった。
粒状有機物については、養殖筏台数の削減効果が表れている。身入りも非常に良くなり生産性の向上と環境負荷の低減が両立することが明らかになった。
これらの結果をもとに、「志津川湾の将来を考える研究会」などで検討を進めている。ASC認証の取得にもこれらの研究データを提供しており、2016年3月30日に認証を取得することができた。
4 生態系サービスの経済評価・統合沿岸管理モデル
(立命館大学 仲上 健一)
現代の沿岸海域は大きく変化しているが最も大きな課題は人口減少と高齢化であり、これらは沿岸地域で極端でありこれらの地域は「消滅地域」と呼ばれている。沿岸域において「持続可能な里海」という考え方で「きれいで豊かで賑わいのある海」により消滅を防ぐためのプロジェクトを研究している。里海を軸として自然・社会・経済をもとにサスティナビリティを考えていきたい。
「環境の価値を測る」ことについては、林野庁による森林の公益的機能の経済的評価の例がある。21世紀になり「生態系サービス」という言葉が定着してきており、これには、調整・基盤・保全・文化・供給サービスがあり、それぞれの指標を基に瀬戸内海の環境価値は20年前の調査により454兆円と試算されている。また、環境省でも干潟についての経済評価がなされ1昨年5月の発表で6103億円とされている。これらが説得力を持つためには、環境哲学・倫理学、住民意識などを勘案した生態系サービスの理解が必要となる。
生態系サービスのフレームワークとして三陸(志津川)・日本海(七尾湾)・瀬戸内海(日生)という3地域を設定しており、20~100キロ範囲でアンケートにより広域レベルでの愛着分布調査を行い表明選好法・仮想評価法(CVM)で解析を行った。広島湾においては仮想評価法(CVM)により下水処理場の処理能力の変更それに要する経費の負担と、水のきれいさやカキの量の関係などのシナリオを設定しアンケート調査を行った。この結果、カキの価値は市場価値と非市場価値の合計であり、下水処理場のコントロールによる栄養塩管理法の提言もできるデータができつつある。
コスタンザ評価手法を適用して計算した結果と比較したところコスタンザの計算結果とはかなり開きがあるが、日本全体の干潟の価値は約500兆円と試算された。
これらをもとに、「沿岸域管理の段階的管理法」を提案するとともに、「魚食や和食」に関する調査や「協働の海洋学」として、MPAの提案にむけた取り組みなどを行っている。
5 日本海の海域管理法の開発
((公財)環日本海環境協力センター 吉田 尚郁)
日本海グループでは、気候変動に伴う海水温上昇と降水量の変化による影響及び日本海の上流域である黄海・東シナ海からの栄養塩負荷の影響、という日本海で特に問題になる2つの事象について注目している。
これら2つの問題がどのように日本海の環境や低次生態系に影響を及ぼすのかを予測し、これらの影響をどのように監視し、どのように管理するのかといったことを日本海管理として取りまとめて提案していきたい。
予測については、低次生態系モデルと高次生物輸送生残モデルを開発し、気候変動・栄養塩変動・南水北調の3つのシナリオにより日本海の環境の将来変動のシミュレーションを行う。
低次生態系モデルでは植物プランクトンを細かく再現する愛媛大学のモデルと、より長期に変動を計算できるモデルとして九州大学のモデルを開発し、数値モデルでの実験を進めている。高次生態系についてはスルメイカとズワイガニを対象とした卵・幼生の輸送生残モデルを開発した。
このモデルをもとに、いつ・どこに・どういった影響が現れるのかを数値実験した結果、栄養塩の負荷の変化の影響は日本海の東北沖に翌年の4月に現れること、物質循環・水塊形成のメカニズムの解析によりそれぞれの海域における起源水の変動などが明らかになった。これらのメカニズムを解明することにより、中国や韓国とともに上流域(東シナ海)で、未然に影響を発見するための監視体制を構築していきたいと考えている。日本海の重要生物の保全に関しては、環境変化や生活史に合わせて海洋保護区を適用する「ダイナミックMPA」を検討していくほか、生態系モデルを使って富山湾を対象とする「海域ヘルシープラン」を提案していきたい。
日本海の管理には対岸諸国や上流域との連携が必要であり、このため、国際連携組織であるNOWPAPを利用していきたい。
6 日本海低次生態系への東シナ海からの影響
(愛媛大学 森本 昭彦)
日本海は東シナ海の影響を受けているが、東シナ海の上流では三峡ダムや南水北調の影響により海洋環境が変化していると言われており、ここでは低次生態系に着目してモデルにより上流域である東シナ海や黄海が変わったときに日本海に何が起こるのかを研究する。
この研究では、栄養塩と植物プランクトン・動物プランクトン・デトリタスの沈降および微生物による分解という流れを考えていく。栄養塩は表層よりも深層の方が多く、上昇流や混合によって表層に運ばれる、というプロセスで低次生態系が成り立っている。日本海(対馬海峡)の夏季では深層のほうが表層よりも栄養塩が多く分布している。一般的には冬季の海面冷却により海水の混合が起こるが、日本海では対馬暖流の影響で水や物質を水平に運んでいる。栄養塩は対馬海峡から日本海に運ばれていくということを考慮しなければならない。10年間程の実測の結果では栄養塩の対馬海峡からの流入量は夏と秋に多い。長江の流量は信濃川の64倍もあり、長江の倍以上の膨大な栄養塩が日本海へ流入していると考えられる。また、窒素濃度は年によりかなり変動することが分かっている。
九州大学が開発した物理モデルによりプランクトン分布の変化を計算したところ、4月に最も濃度が高く、夏に減少し、秋から冬にかけてまた多くなるという結果になった。これを人工衛星データの解析結果と比較すると、実際によく再現されている。
このモデルにより、対馬海峡から流入する栄養塩の量の変化により植物プランクトンの量がどうなるかを計算できる。20年間1.5倍の栄養塩を流入させ続けてもプランクトン量はほとんど変わらないという結果になったが、シナリオにより検討する必要がある。また、有害プランクトンが増えるかどうかは今後の検討課題である。さらに、日本海に面した富山湾や若狭湾等、日本の沿岸域がどう変化するかを今後調べる必要がある。
7 日本海低次生態系の将来変動予測に向けて
(九州大学 広瀬 直毅)
日本海は特に水温上昇が大きい海域であり生態系への影響も大きいと考えられる。この研究では単純化した生態系モデルである「DREAMS2」により低次生態系の将来予測を行う。溶存酸素に着目して取り組んでいることが特徴である。日本海は他の海域とは異なり、底層まで溶存酸素濃度が高く、酸素が生物に消費されない状態で新鮮な水で満たされていることが特徴であり、これを再現できることが精度が高い優れたモデルということになる。このため、パラメーターを現実的なものとすることを目標にする。例えば、デトリタスの沈降速度を検討することにより再現性が向上する。しかし、個々のパラメータを一つ一つチューニングするのではなく、多くのパラメーターを一気に行うため「データ同化」による逆推定を行いモデルの最適化を行っている。観測データとしてWOD13に収録されているデータを用い最適化を行いパラメーターを推定し、DOについて、生態系がある場合とない場合の比較実験を行った結果、観測データを十分な精度でよく再現することができたと考えている。
最適パラメーターによる計算結果では、DINやクロロフィルは観測データとよく一致した。溶存酸素はプランクトンの影響の有無による濃度変化をよく解明することができた。溶存酸素の経年変化の再現結果は減少傾向にあり、これは水温上昇によるものと考えられる。低次生態系のパラメーター経年変化を再現すると、栄養塩・植物プランクトン・動物プランクトン・デトリタスのいずれもが単調に減少しており、生物環境は良くなっているとはいえいない。過去の状態と比較して予測に耐えるモデルになっているかを明らかにして将来予測に取り組んでいきたい。
物理生物モデルとして「DEAMS2」により検討した結果、日本海の生態系環境は弱化していると考えられた。
8 スルメイカ・ズワイガニへの環境変動の影響
(愛媛大学 郭 新宇)
この研究では、スルメイカとズワイガニについて過去20年間の資源量の再現を行い、高次生態系の視点から環境変動応答を予測し、海洋保護区による環境管理の効果を検証しようとしている。
スルメイカについては産卵場や生態特性などに関する豊富な知見があり、これをもとにモデルを構築した。漁獲量は3倍程度、資源量は4倍程度変動しているが、これは親魚の数の影響が最も大きいためと考えられる。ふ化幼生の初期分布を特定し、親魚の数、輸送、鉛直移動等を考慮して経年変動を計算したところ、観測値とよく整合している結果となった。このことから、海洋保護区(MPA)を設定して親魚の数を減らさないように管理すれば資源の増加は期待できると考えている。
ズワイガニは、スルメイカとは違いあまり大きな移動はせず、寿命は10年以上である。漁獲量は経年的に大きく変化しているが、京都府などでは海洋保護区がすでに作られて効果が出ているとの報告があり、海洋保護区が資源保護に役立つと考えている。
数値シミュレーションでは幼生の分布を再現する。水平成分、鉛直成分、生残条件を設定し120日間の粒子追跡計算を行った結果、経年的な変動の傾向はおおよそ合っている。1998年と2006年では中規模渦の存在が大きく異なっており、生物的要素はあまり経年変化に影響を与えないが、流動場の違いによる影響が強いと考えられ、「中規模渦」の存在が強く影響していると考えられた。
モデルの解像度を細かくして湾レベルまで計算することができるようにする、また、MPAの場所、将来の日本海の物理環境に対する応答特性についても検討することが今後の課題である。